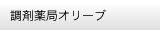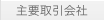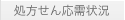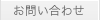お薬の話
お薬の正しい飲み方
病気を治すお薬も、正しく飲まないと逆に具合が悪くなったりします。貴方のお薬の飲み方は大丈夫ですか?
- しっかりと水分をとりましょう。
 水分が少なすぎると薬は溶けにくいもの。少なくともコップ半分くらいの水(100ml程度)で、しっかりと胃に流し込むことが大切です。
水分が少なすぎると薬は溶けにくいもの。少なくともコップ半分くらいの水(100ml程度)で、しっかりと胃に流し込むことが大切です。
特にカプセルは水分が少ないと薬が食道で止まってしまい、粘膜を傷つけることがあります。水分摂取を制限されている方は薬をどのように飲めばよいか、医師に相談してください。- 錠剤やカプセルはかまないで!
 錠剤やカプセルはゆっくりと溶け出して、効果を長時間持続させるように工夫して作られており、胃の粘膜を荒らさない利点もあります。
錠剤やカプセルはゆっくりと溶け出して、効果を長時間持続させるように工夫して作られており、胃の粘膜を荒らさない利点もあります。
でも、かみくだいたり、カプセルを開けて飲んだりしては、その効果が得られません。- 包装は外しましたか?
 錠剤やカプセルをシートからはずさずにそのまま飲んでしまい、のどや食道を傷つけてしまう事故が少なくありません。とくに高齢の方は気をつけてください。
錠剤やカプセルをシートからはずさずにそのまま飲んでしまい、のどや食道を傷つけてしまう事故が少なくありません。とくに高齢の方は気をつけてください。- 粉ぐすりの上手な飲み方
- 粉ぐすりを飲むとむせたり、口の中やのどに残ってしまいやすい方は、先に少量の水分をとって口の中とのどをうるおしてから薬を飲むようにすると楽に飲めます。
- 夜間の服用や横になっている方は…
- 寝た姿勢のまま薬を飲むと、薬が食道で止まってしまうことがあります。薬を飲むときはなるべくからだを起こすようにしましょう。
服用時間の正しい意味

薬にはなぜ「食前」「食後」など飲むべき時間が決められているのでしょうか?
その理由は、胃の中に食べ物があるかどうかが薬の作用に影響するためです。
さて、あなたは服用時間の「ことば」の意味を正しく知っていますか?
- 「食前服用」
- 食事の約30分前に飲む、という意味。おもに胃の中で食物と結合すると吸収されにくくなる薬や胃腸の働きを活発にする薬、即効性が求められる場合などに用いられます。
- 「食後服用」
- 食事の約30分後に飲む、という意味。胃の中に食物が残っている為、薬が直接胃の粘膜を刺激することなく、おだやかに吸収されます。飲み忘れそうな方は、食後すぐに飲んでもかまいません。
- 「食間服用」
- 食事と食事の間の空腹時に飲む、という意味。食事の2時間後がめやすとなります。胃の中に食物がほとんど残っていない状態ですので、薬をより速く吸収させ、的確に効果を発揮することができます。
- 「時間ごと服用」
- 例えば「6時間ごと」のように、食事に関係なく一定の間隔で飲む、という意味。抗生物質など、薬の効き目を長く一定に保つことができます。ただし、深夜の服用は睡眠のさまたげにならない程度の間隔でかまいません。
- 「就寝前服用」
- 寝る30分前に飲む、という意味。消化性潰瘍の薬など夜間の症状をおさえるための薬や睡眠薬などに用いられます。
- 「頓服(とんぷく)」
- 痛みなどの症状があるときだけ飲む、という意味。胃の痛みや歯痛、頭痛、生理痛などに用いられます。
薬の疑問、これで解決!
薬のこと、もっと知りたいあなたへ。良くある質問をまとめてみました。
- Q. お薬はジュースやお茶、牛乳で飲んでもいいの?
- A. 水以外の飲み物の成分(お茶のカフェインなど)には、薬の成分に影響を与えるものがあり、効き目が弱くなったり、強くなりすぎたりすることがあります。水かぬるま湯で飲むようにしましょう。
- Q. 薬を飲むには「湯冷ましがよい」ってホント?
- A. 本当です。冷水に比べ、湯冷ましやぬるま湯は胃を冷やさないので、胃の働きをさまたげず薬の吸収をよくします。
- Q. 「食後服用」の薬を飲んでいますが、食事が 取れなかったときはどうしたらいいのですか?
- A. 食事をしなくてもその時間に薬を飲むのが原則ですが、糖尿病の薬など、食事と密接な関係のある薬もあるので、医師に相談してください。
- Q. お薬をのむのを1回忘れちゃった!次に2回分飲んでもいい?
- A. 飲み忘れたからといって、勝手に量を増やすのは副作用や事故のもと。余分に飲んだりせず、決められた1回分の量を守りましょう。
目薬(点眼薬)の正しい使い方
目薬(点眼薬)の正しい使い方
- 手を綺麗に洗いましょう。
- 顔をやや上向きにし、下まぶたを手で下げ、視線を上向きにします。
- 容器の先が触れないように、目薬を1滴さします。
- 目を軽く閉じて、約3分間、目がしらの少し下を指で押さえます。
- 2種類以上の目薬を使用するときは、点眼する間隔を5分以上あけましょう。
- 点眼液の使用により、目の充血、かゆみ、はれ等異常があらわれた場合には、 使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
目薬を使うときの注意点
- 目薬は1滴で十分です。1滴を確実にさしてください。
- 決められた点眼回数を守りましょう。
- 目薬をさすのを忘れてしまった場合の対処方法は、目薬によってちがいます。 必ず主治医に聞いておきましょう。
保管について
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- とくに指示のない場合は、直射日光をさけ、なるべく涼しいところにフタをきっちりしめて保管してください。